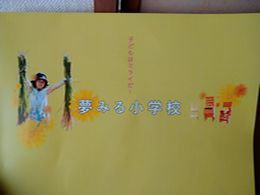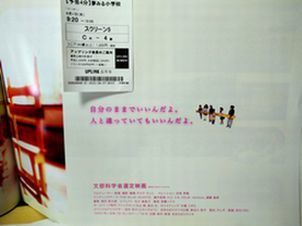ドキュメンタリー映画「夢みる小学校」 子どもはミライだ!
2022年5月7日(土)
もう1か月前になってしまいますが、「夢見る小学校」というドキュメンタリー映画を観ました。
その学校は「きのくに子どもの村学園」といって、理事長で学園長でもある堀信一郎氏が作った学校です。堀氏は教育学を学んで僻地の教師を目指していましたが、教育学者ニイルがイギリスで開校した「世界で一番自由な学校」と呼ばれている「サマーヒル・スクール」のような、子どもが主役の学校を作りたいと考えました。ニイルの「自由教育思想」に米国の教育学者デューイの「問題解決学習」を加え、日本の伝統風土を生かした独自の教育体系で子どもたちを自由にのびのび育てたいということで、まず和歌山県に「きのくに子どもの村学園」を開校し、その後福井、山梨、北九州、長崎と全国で五つの学校が生まれました。
この映画の主な舞台となっているのは山梨県南アルプス市にある「南アルプス子どもの村小学校」。この学校には学年ごとのクラスがなく、衣食住をテーマにしたプロジェクトから自分の好きな活動ができる場所を自分のホームルームに選んで1年間在籍するそうです。
映画では体験学習を通じて自分たちで問題を見つけて解決策を探し、失敗しながら色々な知識を得ていく、活き活きした子ども達の様子を追っています。
また、この学校には先生と呼ばれる人は存在しなくて、ニックネームで呼ばれるおとなが子どもたちと共に歩む「アドバイザー」的な役割を担っています。
個々の体験には点数がつけられないとして、序列をつけるためのテストもなく、「通知表」ではなく「生活と学習の記録」という、おとなが丁寧な文章で子どもたちの様子と成長を記録したお知らせが届けられます。
映画の中には通知表がない公立小学校として、長野県伊那市立伊那小学校が紹介されていて、1年生がヤギの世話を通して総合学習を行っている様子が映し出されています。やはりここでも子どもたち自身が自分の体や五感の体験を通して自ら育っていくことを大切にして、通知表の代わりに子どもの育ちの姿を直接保護者に伝えることを重視しているそうです。
もう1校紹介されている世田谷区立桜丘中学校の西郷孝彦校長は、理由のない校則をなくし、たった一つの校長ルールとして「中学校3年間を楽しく過ごしてもらうこと」を掲げています。また、生徒総会で決まったことを教師はできるだけ実現すると公言し、定期テストをなくしたいという議題が出て決まった時には実際に定期テストもなくしたそうです。楽しければ学校に行きたいと思うし、自分たちで考えたことが実現されれば、自ら考える力も育つのだろうなと思います。「楽しい」ってなかなか意味の深い難しい言葉だなとあらためて感じました。
全編を通して子どもたちの活き活きした眼差しとそれを見守るおとなの深い愛情が印象的で、これからは、生きる力を育むことがおとなの大事な役割、さらには責任になるのだろうと感じました。また、ある大学の教授が、子どもの村を卒業して自分のゼミに入ってきた生徒は、質問する力が備わっているとコメントされていたことがとても心に残りました。